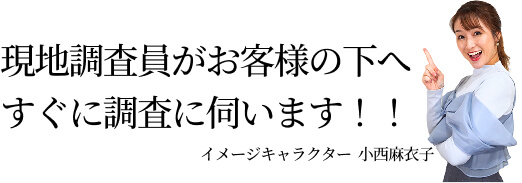【アパート 防水塗装】築20年でも蘇る!老朽化対策の決定版

1. はじめに
アパート経営をしていると、必ず直面するのが「建物の老朽化」です。
外壁や屋根と同様に、見落とされやすいのが防水工事。特に屋上やベランダ、共用廊下などの防水層は、築10年を過ぎる頃から劣化が始まり、築20年を迎える物件では雨漏りや下地の腐食が顕著になっているケースも少なくありません。
「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにした結果、雨漏りが発生してしまえば、入居者の退去や修繕費の膨張につながり、経営に大きな打撃を与えます。
一方で、適切なタイミングで防水塗装を行えば、建物は見違えるほど蘇り、資産価値を長期にわたって維持することが可能です。
この記事では、防水劣化を放置するリスクから、長期的に得する防水塗装のポイント、修繕計画の立て方、さらに実際のメリットまでを体系的に解説します。
2. 防水劣化を放置するデメリット
2-1 構造体への深刻なダメージ
防水層に小さなひび割れや剥がれが生じても、初期段階ではオーナー自身が気づきにくいことが多いものです。
しかし、その小さな隙間から侵入した雨水は、時間をかけて内部へ浸透し、やがて構造体にダメージを与えます。
- 鉄筋コンクリート造の場合:鉄筋が錆びて膨張し、周囲のコンクリートを押し広げ、さらにひび割れが拡大。構造強度の低下を招きます。
- 木造の場合:木材が腐食し、白アリ被害を誘発。耐震性能や耐久性が著しく低下します。
一度内部にダメージが及ぶと、塗装や簡単な補修では解決できず、「下地補修」「躯体補強」「大規模修繕」といった重工事が必要に。最悪の場合、部分的な建て替えが必要になるケースもあります。
2-2 入居者の快適性低下
防水が劣化したアパートでは、雨漏りや床材の膨れ、共用廊下の水たまりといった不具合が頻発します。
こうしたトラブルは入居者にとって大きなストレスとなり、物件への不信感を募らせます。
「天井から水が落ちてくる」「壁紙がシミだらけ」「ベランダの床がボコボコして危険」
こうした状況が続けば、入居者は早期退去を検討し、新規入居希望者にも敬遠される結果に。
さらに口コミやインターネットでの評価が悪化すれば、物件全体の入居率低下につながります。
オーナーにとって防水劣化を放置することは、「安定した家賃収入」を失うことと同義です。
2-3 修繕費が膨らむ
防水工事を計画的に行えば、数十万円〜数百万円程度で済む工事も、劣化を放置すると桁違いの費用に跳ね上がります。
ケース例
- 屋上防水を放置 → 雨漏り発生 → 室内天井クロス・断熱材・電気配線まで交換が必要
- ベランダ防水を放置 → 下階の天井にシミ → 入居者トラブル補償やリフォーム費用が発生
結果的に「防水塗装だけで済んだはずが、内装工事まで必要になった」という事態は珍しくありません。
修繕費が数百万円〜数千万円規模に膨らむ前に、計画的な防水塗装を行うことが最も経済的です。
3. 長期的に得する防水塗装のポイント
3-1 適切な防水工法を選ぶ
防水工事には複数の工法があり、部位や予算に応じた選択が重要です。
- ウレタン防水(耐用10〜12年)
液体を塗り重ねる工法で、複雑な形状にも対応可能。コストを抑えやすい。 - FRP防水(耐用12〜15年)
硬化すると非常に強固で、ベランダやバルコニーに最適。耐久性と軽量性を兼ね備える。 - シート防水(耐用15〜20年)
ゴムや塩ビのシートを敷設。屋上などの広い面積に有効で、耐用年数が長い。
築20年を超える物件では、防水層の再施工に加えて下地補修が必要になるケースも多いため、多少費用がかかっても高耐久の工法を選ぶことが長期的な得につながります。
3-2 足場を効率的に使う
防水工事と同時に外壁塗装や屋根修繕を行うことで、足場費用を一度にまとめられます。
足場代は工事総額の20〜30%を占めるため、複数工事を同時施工することで数十万円規模の節約が可能です。
また、工期短縮や入居者への負担軽減にもつながるため、オーナーにとって合理的な選択となります。
3-3 定期点検とメンテナンス
防水層は外観から劣化が見えにくいため、5年ごとの点検、10〜15年ごとの再施工を推奨します。
特に屋上やバルコニーは雨風や紫外線の影響を受けやすく、想定よりも早く劣化が進行することも。
定期点検を怠らず、早期発見・早期補修を心がければ、大規模修繕を回避でき、資金計画も安定します。
4. 修繕計画の立て方
4-1 専門家の劣化診断を受ける
オーナー自身が判断するのは難しいため、専門家による診断を受けることが重要です。
ドローンや赤外線カメラを用いた調査では、目に見えない漏水経路や劣化部分を可視化でき、無駄のない修繕計画が立てられます。
4-2 補助金や保険の活用
防水工事も補助金や保険の対象になる場合があります。
- 自治体の省エネ・リフォーム補助金
- 台風や豪雨に起因する雨漏りは火災保険の対象
- 長寿命化リフォーム助成金
これらを組み合わせることで、実質的な負担を大幅に軽減可能です。
「補助金を知らずに全額自己負担」というケースを避けるためにも、制度情報を常にチェックしましょう。
4-3 長期収支シミュレーション
工事を行うかどうかは「支出」だけで判断してはいけません。
防水工事を行わないことで発生する空室リスク・家賃下落リスクを加味した収支シミュレーションが必要です。
例えば、雨漏り物件は入居希望者に敬遠され、1室あたり月5,000円下げざるを得ない状況に。
年間で60,000円、10年で60万円の損失。複数室であれば、工事費を超える大きな損失になります。
長期的な視点で見れば、防水塗装はコスト削減と収益維持の両立を可能にする投資といえます。
5. 防水塗装で得られるメリット
5-1 空室率の低下
防水性能が高い=「安心して住める物件」。
内見時の印象もよくなり、入居希望者が集まりやすくなります。退去率も下がり、結果的に安定収益につながります。
5-2 建物寿命の延長
防水塗装は建物にとっての「傘」。
雨水の侵入を防ぐことで、木材や鉄筋を守り、建物全体の寿命を延ばすことができます。築20年を超えても、適切な防水メンテナンスを行えばさらに数十年にわたって利用可能です。
5-3 修繕コストの削減
定期的な防水工事を行うことで、大規模修繕や建て替えリスクを回避できます。
「小さな投資で大きな損失を防ぐ」ことこそが、防水工事の本質的な価値です。
5-4 資産価値の維持・向上
計画的に防水工事を行っている物件は「管理が行き届いている」と高く評価されます。
売却査定額のアップや、金融機関からの融資評価向上にもつながり、資産価値を守るための重要な施策といえます。
6. まとめ
築20年を迎えたアパートにとって、防水塗装は老朽化対策の決定版です。
「まだ大丈夫」と応急処置や先延ばしを繰り返すと、かえって修繕費が膨らみ、空室リスクも高まります。
長期的に得するためには、
- 工法選びを慎重に行う
- 足場を効率的に活用する
- 補助金・保険を賢く利用する
- 定期的な点検・修繕サイクルを守る
といったポイントを押さえることが重要です。
防水塗装は「出費」ではなく、建物と収益を守るための投資です。
築古物件でも適切な防水対策を行えば、まだまだ収益を生む資産として蘇らせることができます。
お問い合わせ情報
アパートマンション大規模修繕ダイレクト 東三河店
所在地 〒442-0007 愛知県豊川市大崎町上金居場53番地
電話番号 0533-56-2552
問い合わせ先 info@sanyu-tosou.com
会社ホームページ https://sanyu-tosou.com/
YouTubeチャンネルアドレス https://www.youtube.com/@team-sanyu