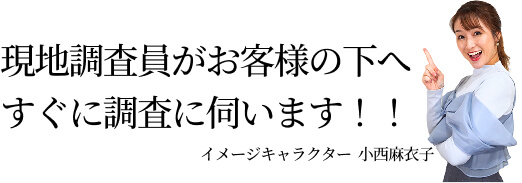【アパート 耐震工事】空室改善に効く!大家さんの成功事例

1. はじめに
築20年、30年を迎えるアパート経営で悩ましいのが「空室リスク」です。
見た目や設備を改善しても、「地震に弱そう」という不安が残る物件は敬遠されやすく、入居が決まりにくくなります。
そこで注目されているのが 耐震工事による空室改善。
実際に耐震補強を行った大家さんの成功事例では、空室が解消されただけでなく、家賃の維持や入居者満足度の向上にもつながっています。
2. 耐震性不足が空室を招く理由
- 内見時に「古くて危なそう」というマイナス印象を与える
- 入居者が更新時に「地震が来たら心配」と退去を選ぶ
- 不動産会社から「耐震工事がされていない」と説明され、他の物件を勧められる
築古物件にとって、耐震性の不足は単なる安全上の問題だけでなく、空室率を押し上げる大きな要因なのです。
3. 耐震工事で空室改善した大家さんの成功事例
3-1 築25年木造アパート:耐震壁増設で入居率回復
愛知県内の築25年木造アパートでは、空室が続き「家賃を下げないと決まらない」という状況に。
オーナーは耐震診断を受け、耐震壁を追加して補強工事を実施しました。
工事後は不動産会社が「耐震補強済み」と広告に明記。内見者から「古いけれど安心できる」と評価され、半年以内に空室がすべて埋まりました。
3-2 築30年鉄骨アパート:基礎補強で長期入居者が定着
築30年の鉄骨アパートでは、長期入居者から「地震が心配」との声が上がり、退去検討の動きがありました。
オーナーは基礎の補強工事を行い、構造全体の耐震性を改善。
その後の更新時には「安心できるから住み続けたい」と長期入居を選ぶ入居者が増え、退去率が大幅に低下しました。
3-3 築20年RCマンション:鉄骨ブレース追加で家賃維持
築20年のRCマンションでは、競合物件との比較で「古く見えるから」と家賃値下げを求められるケースが目立ちました。
オーナーは鉄骨ブレースを追加する耐震補強を行い、同時に外壁塗装と屋上防水も実施。
結果、「安全で管理が行き届いている物件」と評価され、家賃を下げずに新規入居を獲得できました。
4. 耐震工事を「空室対策リフォーム」に変えるポイント
現状を把握するために耐震診断を受ける
空室対策の第一歩は、現状を正確に把握することです。
専門家による耐震診断を受ければ「建物がどの程度の揺れに耐えられるのか」「どの部分に弱点があるのか」を明確にできます。
診断の結果、軽微な補強で済む場合もあれば、基礎や構造全体を強化する必要がある場合もあります。
無駄な工事を避け、最小限の投資で最大の効果を得るためには、まずこの診断が不可欠です。
外壁や屋根修繕と同時に行ってコスト削減
耐震工事は足場を組むケースが多いため、外壁塗装や屋根修繕と同時に行うのが効率的です。
例えば、耐震補強と外壁塗装を別々に発注すると、足場代だけで数十万円〜100万円近い費用が二重に発生してしまいます。
しかし一度にまとめれば、足場を一回組むだけで済むため、大幅なコスト削減が可能。
さらに「見た目の美観改善」と「構造強化」を同時に行えることで、入居者や内見者に対して「リフォーム済みで安心できる物件」と強力にアピールできます。
補助金制度を活用して実質負担を減らす
多くの自治体では、耐震診断や耐震工事に対して補助金を用意しています。
たとえば「耐震診断は無料」「工事費の1/3〜1/2を助成」など、地域によって条件は異なりますが、上手に活用すれば数百万円単位で負担を軽減できる可能性があります。
さらに、工事後には税制優遇措置や地震保険料の割引が適用されるケースもあります。
こうした制度を積極的に調べ、利用することが、オーナーにとって費用対効果を最大化する秘訣です。
「耐震補強済み」を募集広告で強調する
耐震工事を行ったら、必ず「耐震補強済み」という強みを広告や不動産会社を通じて発信しましょう。
ただ工事をしただけでは入居者には伝わらず、せっかくの投資効果が半減してしまいます。
- 募集図面やポータルサイトに「耐震補強済み」と明記する
- 内見時に営業担当者から「安全性が高い物件」と説明してもらう
- 入居希望者には工事内容の資料や写真を提示する
これらを徹底すれば、他の物件との差別化ができ、「多少古いが安心できる物件」として選ばれやすくなります。
まとめ
耐震工事を単なる「修繕」で終わらせず、安全性をアピールする空室対策リフォームとして活かすことが大切です。
診断 → 効率的施工 → 補助金活用 → 情報発信、この流れを押さえることで、投資効果は飛躍的に高まります。
5. 成功事例から見える耐震工事のメリット
空室率の低下:「安心できる物件」として選ばれる
「耐震補強済み」という情報は、入居希望者にとって強い安心材料となります。
同じ家賃帯の競合物件があっても、安全性で差がつけば、選ばれるのは耐震補強済みの物件です。
結果として、空室が減り、稼働率が高まります。
家賃の維持・アップ:相場より安くしなくても入居が決まる
耐震工事をしていない築古物件は「古いから安くしないと入居が決まらない」という悪循環に陥りがちです。
一方で、耐震補強済みの物件は「安全で管理が行き届いている」と評価され、家賃を下げずに募集が可能。
場合によっては「安心できる物件だから多少高くても住みたい」というニーズが働き、相場以上の条件で入居が決まることもあります。
退去率の低下:長期入居につながり経営が安定
入居者にとって、安全な物件は「長く住みたい」と思える条件のひとつです。
逆に耐震性に不安があると、更新時に退去を選んでしまうリスクが高まります。
耐震工事を済ませた物件では、更新率が向上し、退去率が下がる傾向があります。
長期入居者が増えれば、募集・リフォーム・広告といったコストも減り、経営は安定します。
資産価値の維持:売却や融資査定でもプラス評価
金融機関や査定会社は「耐震補強済みかどうか」を重視します。
耐震性が不足している物件は担保価値が低くなり、融資条件が厳しくなったり、売却時に大幅な値下げを求められることもあります。
一方、補強済みであれば「安全で長く運用できる資産」と見なされ、評価が高まります。
つまり耐震工事は、入居率改善だけでなく、資産価値を守る経営戦略でもあるのです。
まとめ
耐震工事には「空室率の改善」「家賃収益の安定化」「退去率の低下」「資産価値の向上」といった多面的なメリットがあります。
単なる安全対策ではなく、長期的なアパート経営を安定させるための投資であり、大家さんにとって欠かせない戦略的リフォームといえるでしょう。
6. まとめ
耐震工事は「安全性を確保するための投資」であると同時に、空室改善につながるリフォーム術です。
- 築古でも「耐震補強済み」と伝えられるだけで印象は一変
- 家賃を下げずに入居率を改善できる
- 入居者に長く選ばれる物件へと再生できる
築20年、30年を迎えたアパート経営者にこそ、今取り入れるべき修繕計画といえるでしょう。
お問い合わせ情報
アパートマンション大規模修繕ダイレクト 東三河店
所在地 〒442-0007 愛知県豊川市大崎町上金居場53番地
電話番号 0533-56-2552
問い合わせ先 info@sanyu-tosou.com
会社ホームページ https://sanyu-tosou.com/
YouTubeチャンネルアドレス https://www.youtube.com/@team-sanyu